「去華就実」と郷土の先覚者たち
第14回 奥村五百子 (下)
奥村五百子の社会運動は、後半生に至って国際的な拡がりを見せます。
(6)兄弟での朝鮮事業
五百子の兄・円心は幕末には尊王の志士として討幕運動に参加したが、明治維新以降は総本山の説得を受け入れ、僧侶としての本務に専念していた。円心は五百子の最も尊敬する人物の一人であった。徳川幕府の時代、外国人への宗教の布教は禁じられていたが、明治期に入ると、東本願寺はいち早く朝鮮半島への布教に乗り出す。円心にその任が与えられた。明治10年(1877年)、円心は朝鮮半島に渡り、5年かけて釜山、仁川、元山の3箇所に東本願寺の別院(及びその支院)を建てた。
明治30年(1897年)6月、東本願寺は円心と五百子の兄妹を京都に呼び、朝鮮半島における布教の一層の強化を求めた。明治27-28年(1894-95年)の日清戦争に勝って、明治政府は半島への進出を強めようとしていた。儒教が中心の朝鮮において仏教を広めることは、両国民の文化的融和に寄与することだから、東本願寺としても国策に呼応する意図があったのだろう。
まず兄の円心が渡って新たな布教拠点を探し、全羅南道の光州をその地と定めた。五百子も数ヶ月遅れて兄の待つ光州へと向かった。
円心がそれまでに寺を開いた釜山、仁川(現在の韓国領)、元山(現在の北朝鮮領)にはいずれも貿易港があり、財閥系商社員を始めとする日本人の居留地があった。これに比して光州は小さな田舎町であり、ここでの事業は、現地の人々への布教という課題を正面に据えた新たなものだった。
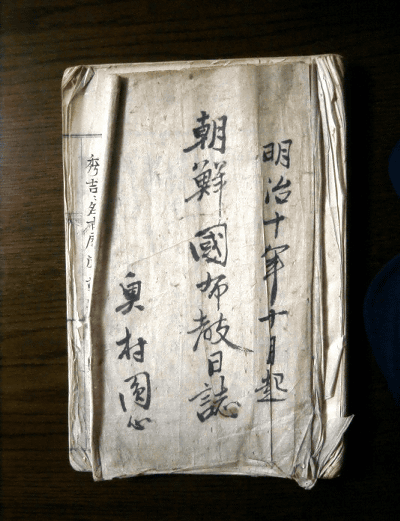
(7)奥村実業学校
光州に渡った五百子は兄円心の布教活動を助けたが、五百子自身の主な関心は、宗教とはやや違うところにあった。それは農業教育である。朝鮮の人々に養蚕や米作の技術を教え、農業技術を改良して生活を豊かにすること、それが長期的には最も大切なことと考えたのだ。そこで五百子は実業学校の建設を決意する。
当時のわが国の支配層にも、武力による朝鮮進出が先行してはならないという考えはあった。彼らは、光州に実業学校を建設するという五百子の考えに共感した。極東の友好、融和は産業・文化の面から行うべきだというのである。貴族院議長・近衛篤麿と外務大臣・大隈重信が支援に乗り出した。明治31年(1898年)9月、「奥村実業学校」が光州に開校し、五百子は東本願寺から校長として任命される。五百子の次女光子とその夫・節太郎が光州に合流して事業を支えた。しかし、日々の暮らしに追われる農民たちを学校に呼ぶこと自体、容易ではなく、加えて抗日感情も強かったので、一軒一軒訪問して農作業の指導をするなど、創設期の苦労を体験する。
五百子は更に、ソウルに徳風幼稚園という名の幼稚園も作り、こちらには長女の敏子を呼んで園長とした。協力者も揃い、54歳の五百子は朝鮮半島を自らの死に場所と定めて事業にまい進した。幼稚園関係者と共に収まった写真には、充実した表情の五百子がいる。しかし冬を経験すると、寒さからくる強度の気管支炎に苦しみ、また人々の抗日感情にも悩み、すっかり弱って翌年、療養のため唐津に戻った。異国での五百子の活躍を知った東伏見宮妃殿下周子(かねこ)はその苦労をねぎらい、ベルツ博士の診察を受けさせた。

右から3人目が奥村五百子、その左に娘の奥村敏子。
他の4人は朝鮮の人々と思われる。
(8)中国南部視察
五百子の気管支炎と胃腸病は慢性化していたが、健康がやや回復したのを待って、東本願寺は五百子に対し、今度は中国南部への布教のための視察を命じた。明治33年(1900年)2月、五百子は門司を出て福建省福州へと向かった。
このころから五百子は、日本女性の代表として国家のために身を捧げる、一種のカリスマとなりつつあった。病躯をおして中国へと渡航する五百子に対して、東伏見宮妃殿下周子は「ますらをも及ばざりけり 国のためこころつくしし 君のまことは」と餞別の歌を贈り、歌人で華族女学校教授の下田歌子は「日の本のまことの種子を もろこしの原にも植えよ やまとなでしこ」と詠んだ。日本の上流階級の夫人たちがこぞって奥村五百子を讃え、その活躍に声援を送った。
五百子の中国滞在中に義和団の乱が起こり、日本を含む8ヶ国連合軍(日英米仏露独伊墺)がこれを鎮圧した。北清事変と呼ばれる。各国に多数の死者が出たので、東本願寺は慰問団の派遣を決めた。五百子は中国南部視察からいったん帰国していたが、新たにこの慰問団への参加を希望し、再度の中国訪問をする。ここで初めて、彼女は戦争の現場に足を踏み入れる。その惨状を目の当たりにして衝撃を受ける。そして、国家のためにこうして死んで行く多数の人々に対して、仏教の使者として、また女性としてそれを慰め、ねぎらう運動をしようと決意する。
(9)愛国婦人会
帰国した五百子は小笠原長生、近衛篤麿(このえあつまろ)など、有力な後援者に自分の考えを伝え、賛同を得た。こうして明治34年(1901年)「愛国婦人会」が設立された。全国の有志から小額の寄金を募り、それをもとに兵隊たちの留守家族や戦没者遺族の生活を援助しようという民間運動である。
近衛の考えが強く作用した結果であろう、「会」は上流階級の婦人たちが呼びかける運動として企画された。39人の発起人が集まったが、そのうち18人は公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の夫人たちであった。岩倉久子、一条悦子、近衛貞子、島津田鶴子、九条恵子、松平充子、小笠原秀子らが名を連ねた。あとの21人は華族外だったが、その多くは高度な学歴を積んだ女子教育界の指導者たちであった。下田歌子(歌人、華族女学校教授、実践女子学院の創立者)、山脇房子(山脇学園の初代校長)、跡見花渓(跡見学園の創立者)、三輪田真佐子(三輪田学園の創立者)、鳩山春子(共立女子職業学校校長)らがいた。少し遅れて華族からは毛利安子、鍋島栄子、細川孝子、黒田清子、松平久子らが、教育界からは津田梅子(英学者、津田塾の創始者)らが加わった
近衛篤麿(このえあつまろ)は藤原鎌足(ふじわらのかまたり)から数えて第45代目の近衛家当主であり、ドイツとオーストリアで法学を学んで帰国し、明治天皇から任命されて当時は貴族院議長と学習院院長を兼務していた。上流社会と政界に大きな影響力を振るったこの貴族政治家が、五百子のような、さしたる学問も地位もなく、情熱と行動力だけで生きてきたような女性と馬が合ったというのも面白いのだが、とにかく、近衛篤麿は五百子の熱心な後援者であった。
愛国婦人会の設立にあたって近衛篤麿は、五百子の情熱と影響力を最大限に活用して上流階級の夫人たちを一気に束ね、大きな国民運動を作ろうと考えたのだろう。その意味で、愛国婦人会を発案したのは五百子だが、その組織と運動のありようについては、近衛、小笠原らの考えが色濃く入っている。
下田歌子が起草した「愛国婦人会趣意書」では、五百子が自らの大陸での活動と体験からこの運動を提唱し、それに賛同した婦人たちが作る組織であると述べられている。従って五百子は「会祖」として別格の待遇を受け、発起人にも常務委員にも入らなかった。このような立場を五百子自身が望んだかどうか分からないが、結果として、中央での「会」の運営は貴婦人たちが行い、五百子は象徴的存在となった。

明治36年(50歳)頃の写真
『下田歌子先生伝』
(国立国会図書館ウェブサイトより)
この自由な立場を生かして、五百子は全国遊説の行脚に出た。明治34年(1901年)4月、京都からこの行脚はスタートした。薬を片手に病んだ老体に鞭打ち、味噌汁と冷飯の食事で、寺など安い施設に泊まりながら、足掛け4年にわたり、1道2府39県で350回を超える演説会を開いた。近代日本の政治史、社会運動史において、一人の人間がこれだけの遊説を集中的に行った例は、他に余りないのではないか。しかし明治37年(1904年)、大分市の壇上で大量の吐血をしたことで、この苛酷な荒行は打ち切られた。

『奥村五百子詳伝』より
貴婦人たちの運動組織として始まった愛国婦人会であったが、全国遊説の効果に政府・軍の支援もあって、数年で50万人以上の会員を抱える巨大組織となった。日露戦争においては、兵士の留守家族や遺族の見舞い、傷病兵の見舞いなどの活動を行った。
日露戦争中、戦局がやや安定すると、療養中だった五百子は戦地慰問を申し出て周囲を驚かせた。明治38年(1905年)6月、対馬沖から旅順、奉天など激戦地を訪れ、敵味方の別なく戦死者に向けて念仏を唱え、また傷ついた人々を見舞った。奉天を訪れたさい、最前線に行きたいという五百子の願いに、満州派遣軍総司令官の大山巌元帥がそれは危険だから許可できないと断ると、「大山を乗り越えて行く道もなし 悲しくもあり口惜しくもあり」という捨て台詞を書き残して軍司令部を去るなど、相変わらずの気の強さを見せた。
(10)最期
日露戦争慰問で病状が限界に達した五百子は、翌年、婦人会の仕事をすべて辞した。送別会は東京九段の偕行社で開かれた。皇族や軍幹部が列席する中、岩倉久子がお礼とお別れの言葉を述べた。自らの理想どおり、職を辞すれば地位も財もなく、ただの老婆として唐津で隠居療養生活を送った。衰弱がひどくなり、周囲が見かねて京都大学付属病院に移したが、明治40年(1907年)2月7日、63歳で死去した。
五百子の葬儀をどのように行うかは、ひとしきり議論になった。結局、五百子が関わった人々の合同葬のようなものになり、国も平民の女性に対するものとしては最大限の敬意を払った。遺体は愛国婦人会京都支部を出て葬儀場である東本願寺大学寮まで行進した。葬儀の主宰者は婦人会総裁である閑院宮載仁親王妃智恵子、その名代を東本願寺法主大谷公演の妻大谷章子が務めた。葬儀委員長は京都府知事大森鐘一であった。
実は閑院宮妃智恵子と大谷章子は姉妹であり、共に三条実美の娘である。幕末の尊王討幕運動の最中、大宰府に逃れた三条実美らに五百子が仕えて以来の縁である。後に東本願寺に嫁いだ章子を、五百子はわが子のように可愛がっていた。遺骨は東本願寺の東大谷納骨堂に納められ、東京の浅草本願寺と唐津の高徳寺にも分骨され、お墓が作られた。

追悼会が各地で催された。特に浅草本願寺で行われた二回忌には5,000人が参列したという記録がある。一周忌には大久保高明による詳細な伝記が出版され、その後、東京九段、横浜、唐津、光州、ソウルなどに銅像が建てられた。
(11)奥村五百子の評価をめぐって
奥村五百子は幕末から明治末期まで、常に時代精神を先駆的に体現して人々を導いてきた。尊王派の討幕運動、自由民権運動、地域産業振興の運動を経て、後半生にはその視野は国際的な拡がりをみせる。朝鮮半島における実業教育と、最晩年の愛国婦人会運動は、いずれも非常に独創的な事業であった。
朝鮮半島における養蚕・米作などの農業指導と実業学校開設、幼稚園開園などは、五百子の社会運動家としてのスケールの大きさが発揮された例である。いっぽう、この事業には、国際人道支援という側面だけでなく、浄土真宗の布教という東本願寺の戦略、及び朝鮮植民地化政策という明治政府の国家的な意図も絡んでいた。奥村五百子はこれらのすべてを意識していたが、どの部分をどう評価するかで、後世の人々の奥村評価は微妙に揺れた。
国家に対する奥村五百子の姿勢は素朴なものであったと思われる。己を捨ててお国のために働くことこそ自分の使命と心得ていた。また、そうした思いが仏教の説く救済の思想と結びついて、彼女の行動を動機付けていたようだ。戦争に対する態度にも、供養という仏教的、母性的、博愛的な要素と、自国の軍隊への協力という両面が混在していた。朝鮮への支援事業などを見れば、奥村五百子が好戦的だったという指摘は当たらないと思うが、時代の動きのなかで避けられない戦争ならば、潔くそれに協力しようという姿勢だったと思う。
奥村五百子の死後、愛国婦人会とは別個にいくつかの婦人組織が作られた。それらはより庶民的であったり、より軍国主義的であったりした。また、愛国婦人会自身の運動内容もしだいに変化した。軍の指導者たちも変わった。時は下って太平洋戦争のさなかの昭和17年(1942年)、国内の婦人組織がすべて「大日本婦人会」に統合された。そして20歳未満の未婚者以外のすべての女性が強制加入させられ、戦時体制への無条件の奉仕という大政翼賛運動の一翼を担った。こうした運動は五百子の説いた供養と援助の精神とは違うものだ。戦時体制下婦人運動の出発点に奥村五百子がいたのは事実だが、死後に発生した極端なひずみの責任を彼女にばかり負わせてしまうのも酷だろう。
奥村五百子が軍隊の力を重視していたのは事実である。列強に侵略されている中国の実情を見て、日本がしっかりせねばという思いを抱いた。中国からの帰途、女性として初めて軍艦宮古に乗り込み、艦上で兵士たちに激励の演説を行っている。
生活態度としては、有名になってからも貧しい暮らしを貫き、死して身の回りに財を残さない、見事なまでに清廉な生涯であった。剛毅直言で傍若無人なところがあったから「カミナリ婆さん」とも言われ、周囲はたいへんだったらしい。それでも要人たちはその本旨を理解し、親愛と敬意を以って接した。外遊中の近衛篤麿に対して小笠原長生が出した悲鳴のような手紙には、母親ほどの年齢の五百子に叱られて困り果てている若き長生の姿があり、微笑を誘うものがある。
「奥村五百子も7月15日帰京つかまつり候(そうろう)。同女は韓国にて吐血つかまつり候。治療のため帰国致し候ものに御座候。されど例によりて気焔万丈、御留守中ゆえ相手は小生一人にて、毎日責めつけられ大閉口に御座候。同女鶴首(首を長く)して閣下のご帰朝相待ち居り、種々申し上げねばならぬと申し居り候」(「近衛篤麿日記」より)。
日本女性の代表として戦前は各地に銅像が建てられた。尾上梅幸主演の演劇が上演され、昭和15年(1940年)には杉村春子主演の映画も作られた。しかし戦後教育の中では語られることの少ない先人となった。
奥村五百子の生涯は、近代日本の政治、軍事、植民地政策、婦人運動、女性の社会活動のあり方、仏教と政治など、非常に多くの問題を含んでいる。このような稀代の女性を歴史に埋もれさせることなく若い世代に伝えて、正当に評価することは大切なことと思う。貴重な史料の取材を許してくださった現在の高徳時住職・奥村豊さんに感謝します。

建つ奥村五百子の銅像

参考文献:
- 大久保高明著 「奥村五百子詳伝」 (1908年 愛国婦人会)(1990年 伝記叢書77として大空社より復刻出版)
- 小野賢一郎著 「奥村五百子」 (1937年 愛国婦人会)
- 三井邦太郎著 「奥村五百子言行録」 (1939年 三省堂)
- 原清編 「小笠原長生と其随筆」 (1956年 創造社)
- 富岡行昌著 「奥村五百子の生涯」 (1995年 郷土先覚者顕彰会)
- 稲葉継雄著 「旧韓末「日語学校」の研究」 (1997年 九州大学出版会)
- 山本茂樹著 「近衛篤麿 ―その明治国家観とアジア観―」(2001年 ミネルヴァ書房)
- 守田佳子著 「奥村五百子 -明治の女と「お国のため」-」(2002年 太陽書房)