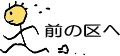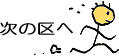127区(連載164回) さくら~上三川
栃木県の全25市町を巡る旅もあと二つ、まずはさくら市で、ここは氏家町と喜連川(きつれがわ)町がいわゆる平成の大合併を経てできた市。自治体が合併する場合、明らかに規模の違いがある時には、大きいほうが小さいほうを吸収合併するかたちになるが、そうではない場合には新しい名称をどうするかが大きな問題になる。古くは東京都の大森と蒲田が合わさって大田区になったとか、国分寺市と立川市の間にあるから国立市だ、といった例があるが、氏家と喜連川ではどう組み合わせても語呂がしっくりこないし、どちらも歴史ある町だから、新しい市の名前を決めるのは容易ではなかっただろう。結果、さくら市という、まぁどちらからも文句の出ない無難なところに落ち着いたのだろう、と推察する。さくらといえば千葉県には佐倉市があるし、反対意見もあったようだが、それもそうだろう。
氏家には勝山城、喜連川には大蔵ヶ崎城とどちらも中世の城跡が残っているので行ってみた。勝山城址には、さくら市ミュージアムがあって、あらためて氏家と喜連川の両町が個別に歩んできた歴史を勉強する。
大蔵ヶ崎城址は、全体がお丸山公園という名の公園なっていて、展望タワーやそこまで行けるエレベーターがあるのだが、東日本大震災とその後の大雨で被害を受けて閉鎖されたままになっており、残念だ。では観光施設は何もないかというと、そんなことはない。喜連川には温泉が出ていて、日本三大美肌の湯だそうだ。道の駅には足湯があって自由に入れるようなのだが、足を濡らすのも面倒だし、今さら私が美肌になってどうするのだ、と通過する。三大美肌の湯とは、ここと佐賀県の嬉野温泉と、もう一つは忘れた。すみません。

読めそうで読めないのが上三川町で、ふつうに読めば“かみみかわ”だと思うが、正解は“かみのかわまち”だ。実は県南から宇都宮を目指して国道4号を北上していた際に、この町をわずかに通ったかもしれない。地図で確認しても、町の境をかすって通過したような、そうでないような状態でよくわからない。いずれにしろきちんと味わってはいないので、改めて行ってみる。この町は中央にN自動車の大きな工場の敷地があり、町の東側には鬼怒川沿いに大小の公園が続いている。
その一つ、蓼沼(たてぬま)親水公園内の池に行くと、放し飼いされた大きなかばさんがのんびりと水浴びをしていてびっくりしたのだが、よく見ると本物ではないのでご安心ください。

これにて、栃木県の全25の市と町をこの足で走った歩いたことになる。私の栃木愛は同県出身のスーパースターU字工事並みだと思っているのだが、どうだろう。栃木県の魅力は一言では言い表せないが、25言なら表せるかもしれないので、ほぼ訪れた順に書いてみよう。
秋なのにひまわりが咲いていた野木町、ゴルフ場の中に古墳があった小山市、餃子祭りには当社も参加している宇都宮市、野球は大谷・栃木の石は大谷(おおや)石・でも大谷(だいや)川が流れていた日光市、鹿沼土の地層に興奮した鹿沼市、国分寺跡は何もなくて逆に良かった下野市、寒風の中でかんぴょうが転がっていた壬生町、岩下の新生姜はここです栃木市、新聞に掲載するいちご企画では毎春お世話になっている真岡市、とうもろこし畑が印象的だった市貝町、濱田庄司氏の焼き物を鑑賞した益子町、駅のそばに軍事遺産があった茂木町、馬頭高校の水産科ががんばっている那珂川町、小松菜スープのちゃんぽんがおいしかった高根沢町、昨年開業した路面電車LRT(ライトライン)の終着は芳賀町、乗った列車が充電式だった那須烏山市、那須疎水の源を見た那須塩原市、高原の風景を満喫した那須町、おしらじの滝の滝壺は深い青色だった矢板市、尚仁沢の湧き水があった塩谷町、マラソンでは苦い思い出の大田原市、社員の弟さんがラーメン店をやっている佐野市、鍋島焼と伊万里焼のコレクションに遭遇した足利市、氏家も喜連川もお城に行ったさくら市、神社には平和を願う大きな剣があった上三川町。以上、まだまだ良いところがある栃木県でした。

2024年12月